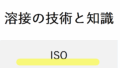金属を接合するには、基本的にボルトによる接合と、溶接による接合との2種類となります。
| ボルト | 溶接 |
|---|
| 変形や残留応力が発生しない | 水密性・気密性に優れる |
| 材質変化が生じない | |
| 高度な技術が不要 | 溶接に関する技術が必要 |
接合エネルギー
| エネルギーの分類 | 溶接方法 | 種類 |
|---|
| 電気的エネルギー | アーク溶接 | サブマージアーク溶接 |
| ティグ溶接 |
| セルフシールドアーク溶接 |
| エレクトロガスアーク溶接 |
| プラズマアーク溶接 |
| ミグ溶接 |
| マグ溶接 |
| 被覆アーク溶接 |
| アプセット溶接 | |
| 科学的エネルギー | ガス溶接 | |
| テルミット溶接 | |
| 力学的エネルギー | 圧接 | 摩擦攪拌(まさつかくはん)接合 |
| 光エネルギー | レーザー | |
詳細
🔧 溶接の特徴
✅ 溶接とは?
金属同士を加熱・加圧・溶融などで接合する方法。接着やボルト接合と違い、一体化した構造が得られるのが特徴です。
🔶 主な溶接の特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|
| 強固な接合 | 溶融・圧接によって母材と一体化し、強い接合が可能 |
| 軽量化に有利 | ボルトやリベット不要。構造をシンプルにできる |
| 気密性・水密性が高い | 配管・圧力容器・タンクなどに最適 |
| 自動化が可能 | 溶接ロボットや自動ラインで大量生産に対応可能 |
| 高温・熱影響あり | 材料が熱で変質・変形・ひずみが生じる場合がある |
🔧 溶接の欠点(留意点)
| 項目 | 内容 |
|---|
| 残留応力・ひずみ | 熱収縮で内部応力や変形が生じることがある |
| 割れ・欠陥のリスク | 気孔・ブローホール・割れなどの欠陥が生じる可能性あり |
| 技能が必要 | 特に手動溶接は職人技や熟練が求められる |
| 母材と異種材接合の難しさ | 金属の組み合わせによっては難しい(例:アルミと鉄) |
🔥 溶接に使われるエネルギー
溶接では、熱エネルギーまたは機械的エネルギーなどを使って材料を接合します。
✅ 主なエネルギーの種類と対応溶接法
| エネルギー種別 | 溶接法の例 | 特徴 |
|---|
| 電気エネルギー | アーク溶接(被覆アーク、MAG、TIG) | アーク放電により高温(約6,000~10,000℃)を発生させる |
| ガス燃焼エネルギー | ガス溶接(アセチレン+酸素) | 可搬性が良いが温度は低め(約3,000℃) |
| レーザーエネルギー | レーザー溶接 | 高精度・高速・狭小部も溶接可。自動化向き。 |
| 電子ビームエネルギー | 電子ビーム溶接 | 真空中で高出力。精密かつ深い溶け込みが得られる |
| 摩擦エネルギー | 摩擦圧接、摩擦攪拌溶接(FSW) | 溶融させずに圧力+摩擦熱で接合。異種金属も可。 |
| 超音波エネルギー | 超音波溶接 | 主に樹脂や薄板金属の接合に使用 |
🔥 アーク溶接の熱源としての特徴
- アーク温度:約6,000〜10,000℃
- 溶接棒/ワイヤ先端と母材との間にアーク放電を生じ、局所的に金属を溶かして接合
- 熱影響部(HAZ)の温度管理が重要
✅ エネルギー効率の比較(代表例)
| 溶接法 | 熱効率(目安) | 特徴 |
|---|
| ガス溶接 | 約30% | 低温で制御しやすいが効率は低い |
| アーク溶接 | 約60% | 一般的な構造溶接に最も使用される |
| レーザー溶接 | 約90% | 高精度・高速・低歪み、自動化に向く |
| 摩擦攪拌溶接(FSW) | 約80% | 固相接合で歪みが少なく異種金属も可 |
✅ まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 溶接の特徴 | 強固・軽量・気密性◎、だが変形・欠陥リスクもあり |
| 使用エネルギー | 主に熱(アーク・レーザー・ガス)や摩擦など |
| 適用例 | 構造物・配管・電子部品・車体・航空機など多岐にわたる |