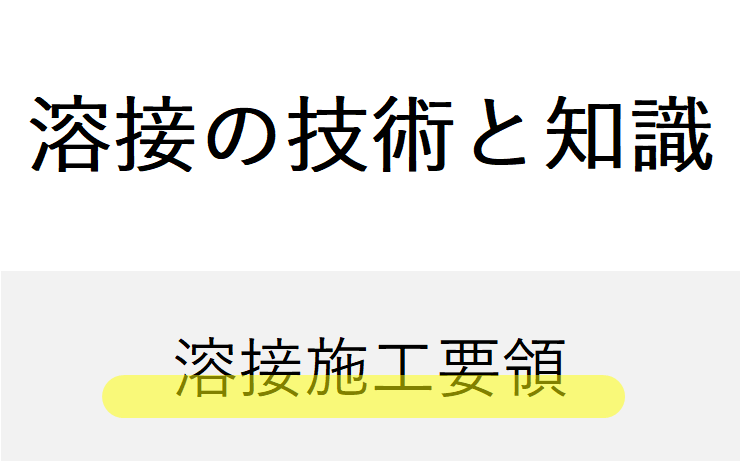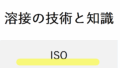金属材料の溶接施工要領及びその承認-溶接施工法試験
- 板の突合わせ多層溶接継手で、試験材の板厚が20mmの場合、承認される板厚範囲は10mm-40mmとなる。
- 溶接施工法試験では、継手引っ張り試験、継手曲げ試験、目視試験が要求されるが、溶接金属引張試験は要求されない
- 片面溶接で試験材を溶接した場合、片面溶接と両面溶接と裏当て金溶接が承認される
- 試験材の予熱温度が100℃の場合、承認される予熱温度の下限は100℃である
- 試験に80%Ar+20%CO2のシールドガスを用いるマグ溶接を行った場合、承認されるArの混合比率は80%である
溶接管理者技術者として、溶接施工時に割れが発生した場合、その原因の推定の為に実施すべきこと
- 割れの状況調査
⇒割れの形状・寸法、位置、深さ、特徴(形状)、発生範囲などを、破面観察、マクロ試験、ミクロ試験、非破壊試験などで調査する - 記録類の確認
⇒母材及び溶接材料の化学組成、炭素当量、PCMなどを材料証明書(ミルシートなど)により確認する
⇒該当溶接継手に適用された溶接法、溶接材料、溶接条件、予熱条件などを確認する。また、当該継手のWPS(溶接施工要領)を確認する
⇒当該溶接継手の溶接時の環境、開先検査結果、非破壊検査結果などの必要な記録を確認する - 上記以外に実施する項目
⇒関連資料及び文献の調査
⇒事故事例の調査
⇒割れの再現試験など
板厚30㎜の780N/㎟級高張力鋼をマグ溶接する場合の、溶接施工における次の5項目について答えよ
- 予熱の目的は何か
⇒溶接部の硬化を防ぎ、拡散性水素の放出促進により低温割れを防止する - 標準的な予熱温度はいくらか
⇒50℃-100℃ - 直後熱とは何か
⇒溶接完了直後に行う溶接部の加熱 - 標準的な直後熱の温度と保持時間はいくらか
⇒200℃-350℃、30分-2時間程度 - パス温度の上限を設定する目的は何か
⇒溶接部のじん性及び強度の低下防止
低炭素鋼のマグ溶接において、ボロシティの発生を防止するための施工上の留意点
- シールドガス流量を適正にする(一般にマグ溶接のシールドガス流量は15-25ℓ/分である)
- 開先部の汚れ(油、塗料、錆、水分など)を除去する
- 防風対策をする(トーチ近傍の風速を2m/分以下にする)
- 溶接速度を遅くし、溶接入熱を適正範囲内で増大させる
- ワイヤの錆、汚れ、吸湿に注意する
- 空気を巻き込まないように、適正なアーク長、ノズル高さで施工する
- 過大なウィービング幅を避ける
- ノズル内面を清掃する。過度のスパッタが付着するとシールドガスの流れが悪くなる
- 雨天、強風時には屋外作業を中止する
次の気象条件下におけるマグ溶接作業において、施工管理上留意すべき事項を簡潔に説明せよ
- 【低温度(例えば-10℃以下)での作業の場合】
低温度では、作業を中止するか、適切な手段で母材を加熱して作業を行う。母材が低温度時の溶接では、熱影響部の硬化や溶接部拡散性水素の増加が進行するため、低温割れ発生の危険性が高くなる - 【強風下での作業の場合】
強風かでは、アーク及び溶接池周辺の風速が2m/秒以下になるような、防風対策を施して作業を行う。それが達せいできない程の強風の場合は作業を中断する。アーク雰囲気に吹き付ける風は、シールドガスのシールド状態を乱し、ブローホールの原因となる - 【降雨・降雪下の作業の場合】
降雨・積雪かでは、溶接線及び溶接機全体を覆うことができるような防護装置がない限り作業を中止する。開先面、ワイヤに付着した水分やアーク雰囲気に吹き込んだ水分は低温割れ・ブローホール等の欠陥の原因となるため、雨・雪の完全な遮断はアーク溶接作業での必須条件である