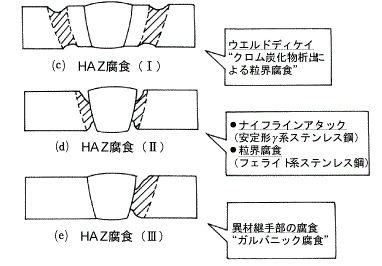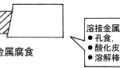1. はじめに
ステンレス鋼は優れた耐食性を持つ材料であり、その特性は不動態皮膜(主に酸化クロム)によって支えられている。しかし、ステンレス鋼に溶接などの熱的負荷が加わると、その局所に組織変化が生じ、腐食に対する抵抗力が低下することがある。このような現象が生じるのが、HAZ(熱影響部)である。
HAZは、溶接時に溶融されることはないものの、加熱により結晶構造や化学成分が変化した領域であり、さまざまな形態の腐食が集中しやすい。本稿では、HAZ腐食の代表的な現象である「ウィルドケイ」「ナイフラインアタック」「粒界腐食」「ガルバニック腐食」について詳しく解説する。
2. 粒界腐食(Intergranular Corrosion)
【概要】
粒界腐食は、ステンレス鋼の結晶粒の境界(粒界)に沿って腐食が進行する現象である。これはHAZで最も典型的な腐食形態の一つであり、溶接時に800〜500℃の温度範囲に一定時間滞留すると、粒界にクロム炭化物(Cr₂₃C₆)が析出する。この析出によって粒界周辺のクロムが局所的に欠乏し、不動態皮膜が維持できなくなるため、腐食が進行しやすくなる。
【影響】
- 腐食が粒界に沿って進行するため、機械的強度が低下し、構造的破壊を引き起こす恐れがある。
- 特に耐食性が重要な化学装置や圧力容器では致命的な欠陥となる。
3. ウィルドケイ(Weld Decay)
【概要】
ウィルドケイとは、溶接によって生じたHAZにおいて、粒界に沿って顕著な腐食が発生する現象を指す。これは粒界腐食の一種であるが、特に母材のHAZに集中して発生することから、独立した名称で呼ばれることがある。鋼材が溶接される際に、HAZ内でクロム炭化物が粒界に析出し、腐食感受性が高まる。
【発生条件】
- オーステナイト系ステンレス鋼(SUS304、SUS316など)で、炭素含有量が高い場合(>0.05%)
- 入熱の高い溶接、または溶接後の冷却が遅い場合
- 高温の腐食環境(Cl⁻や硫化物の存在)
【防止策】
- 低炭素ステンレス(SUS304L、SUS316L)の使用
- 安定化元素(Ti、Nb)を含む鋼種の選定(SUS321、SUS347)
- 溶接後熱処理(溶体化処理)によるクロム炭化物の再溶解
4. ナイフラインアタック(Knife Line Attack:KLA)
【概要】
ナイフラインアタックとは、主にTiやNbを添加した安定化ステンレス鋼に発生する特殊な粒界腐食であり、溶接線のすぐ隣(約0.05~0.5mm)に非常に狭く進行する腐食である。これは、溶接直後の急冷や高温短時間加熱により、安定化元素と炭素が完全に反応できず、未反応の炭素が粒界に残存し、クロム炭化物を析出させることが原因である。
【発生しやすい鋼種】
- SUS321(Ti添加)
- SUS347(Nb添加)
【特徴】
- 外見上は検出が困難であるが、内部に沿って局部的に腐食が進行し、最終的にクラックに発展する。
- 非破壊検査でも見つかりにくいため、構造的に大きなリスクとなる。
【防止策】
- 溶接後の適切な溶体化熱処理(1050〜1100℃加熱 → 急冷)
- 入熱制御による過剰な加熱の回避
- 使用後のパッシベーション処理
5. ガルバニック腐食(Galvanic Corrosion)
【概要】
HAZ腐食の一形態として、異なる金属や合金が電気的に接触し、電解質環境下で電位差によって一方が選択的に腐食する現象がガルバニック腐食である。溶接部では、母材と溶接金属(溶加材)の成分差が原因で、HAZ付近に局部電池が形成されることがある。
【発生条件】
- 異種金属接合(例:オーステナイト系×フェライト系)
- 母材と溶加材の合金組成の不一致(モリブデン含有量の差など)
- 高塩分・高湿度の電解質環境(海洋構造物、冷却水系)
【事例】
たとえば、SUS316L(高耐食性)にSUS308(低Mo)を溶接すると、電位差によりHAZ付近の低耐食部位に腐食が集中する可能性がある。
【防止策】
- 同種または近似合金組成の溶加材を使用
- 表面を研磨し電位差を小さくする
- 絶縁材を介した異種金属接合
- 電解質の遮断や脱塩環境の確保
6. まとめ
HAZ腐食は、溶接によって引き起こされる金属組織の変化に起因する深刻な腐食現象であり、特に以下の4つの現象は注意すべきである。
| 腐食形態 | 特徴 | 防止策 |
|---|---|---|
| 粒界腐食 | 粒界に沿って腐食進行 | 低炭素鋼使用、熱処理 |
| ウィルドケイ | HAZ内に起こる顕著な粒界腐食 | Lグレード鋼、安定化鋼 |
| ナイフラインアタック | 溶接線直近の微細な粒界腐食 | 高温熱処理と急冷 |
| ガルバニック腐食 | 母材と溶加材の電位差による局部腐食 | 合金一致、電解質遮断 |